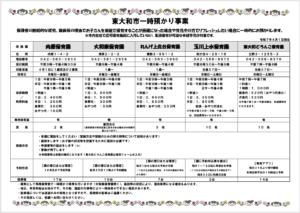【2025年 第1回定例議会報告】一般質問①「子どもと子育てを社会全体で支える」とは?

子育て支援が重視され、経済的支援や育児の負担軽減の支援が進んでいます。しかし子育てを負担と感じる根本的な要因に目が向いているでしょうか。つながりが減り、子育ての経験が継承されない現代。どう子育てしていいか分からなかったり、自分の子育てに自信が持てず孤立感を抱えている状況があるのではないかと思います。気軽に集え、ちょっとした不安や疑問を解消できる場や、親子をおおらかに受け止めエンパワメントするような支援が必要だと考えます。今回の質問の中で、困難を抱える親子への支援は重視されていると感じました。しかし今、子育て親子全体がうっすらとした不安を抱えていて、そういった親子全体への支援が必要ではないでしょうか。それが困難が深まることを防ぐのではないかと思います。
≪ 1.妊娠期から継続して、子どもと子育てを支えることについて ≫
Q)妊産婦への助産師や保健師の戸別訪問や、地区の担当保健師の支援とはどのように行われているのか。
市)妊娠届時と妊娠8か月時に行う全妊婦対象のアンケートで悩みや相談のある人を把握し、伴走型相談支援専任の助産師・保健師が訪問等をしている。
複雑な理由があったり複数の機関で支援を行う必要がある場合は各地区担当の保健師が継続的に支援を行っている。
※「伴走型相談支援」とはいうものの、通常の相談に対しては担当者が継続的に寄り添う、というものではありません。困りごととして顕在化していない問題にも寄り添える体制が必要です。
Q)妊娠や出産、子育てに関して当事者の困難をどのように捉えているか。
市)両親が遠方で育児を手伝ってもらえる人がいない、夫が仕事で忙しく一人で育児と家事を負担しなければならないといったことが相談されている。
Q)「寄り添い、継続して支える」ためにどのようなことが行われているのか。
市)相談や訪問を行なったら、必ず今後の支援プランを立てて電話や面接、訪問などにより状況を把握する体制を整えている。また関係機関との定例の連絡会や、相談員との情報交換や共有を図っている。
Q)子育て親子全体を支える取組みとして、保健センターで対象を限定して行っている専門職を交えた交流会を、子ども家庭センターとして行えないか。
市)保健センターでは双子や発育発達に不安のある親子を対象として、交流や、小児科医・理学療法士・保育士といった専門職に相談できる座談会を実施しているほか、保健師・助産師・栄養士などが随時個別の相談に対応している。誰でも参加できる座談会は今後適切に実施できるよう検討する。
※「相談」になる前の疑問や不安を解消したり、「困りごと」になる前に対処する、といったことこそ必要です。改めて相談しなくても、ゆるやかなつながりの場で問題が深まる前に解消できる、といったために、こういった交流会を有効に機能させることが重要です。
Q)子どもの権利の視点から問題の解決の支援をする「子どもコミッショナー(オンブズマン)」を設置できないか。
市)「子ども相談カード」を小学3年生から中学3年生の児童・生徒へ毎年度配布、また市内の公共施設にも設置し、周知に努めている。
東京都が「子どもの権利擁護専門相談」を実施しており、市独自では、現時点で設置の考えはない。
Q)現状の情報発信について、利用する人からどういった声や意見があるか。
市)市公式ホームページには「欲しい情報を見つけにくい」「説明が分かりづらい」などの意見がある。子育て応援アプリへは地域全体の子育て情報がタイムリーに配信されていないことや、発達障害などの情報が検索しづらいといった意見がある。
Q)子育ての情報の中に、子どもの障害福祉の情報も入れることについて。
市)リンクを貼るなど掲載の改善を検討する。
※現状、東大和市の子育ての情報と障害福祉の情報はまったくつながっていません。子育ての情報を探す中でたどり着けなければ、障害福祉の支援について知らないまま、となってしまいます。その人に寄り添った情報の伝え方、サポートの仕方が必要です。