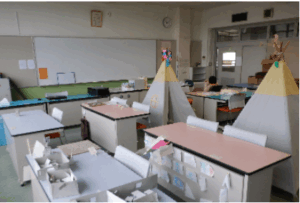【2025年 第3回定例議会報告】一般質問②「食育によりどういったことを目指すか、市のビジョンは」
2025年1月から、学校給食費が無償となり、1食当たりの単価も改定されました。(小学生は学年により300円~340円で50円増。中学生は390円で60円増)市では食育に力を入れていくと言っています。栄養士さんの食育の授業や、畑の体験などが行われている一方で、食べる時間が短いことや、もっと安全性の高い食品にすること、調味料などの質を上げて、本当の味を食べさせるべきではないか、といった声もあります。「食育」の一言で片づけず、何が身につくのか、子どもたちにどうなってもらいたいのかといった「食育のビジョン」がどのようなものか、市の考えを質しました。

≪ 2.学校給食について ≫
Q)単価を上げる前と比べ、食材の選定にどのような違いがあるのか。調味料についてはどうか。
市)肉や魚など、以前より良質な食材を選ぶことができている。調味料は改定前から、学校給食で一般的なもので添加物が少ないもの、原料大豆が遺伝子組み換えでないものなどを使用している。
Q)食材を選定する「基準」は。天然醸造の調味料や、天然塩の使用を規定できないか。
市)食品衛生法等に適合し、「新鮮であること」「不必要な食品添加物を使用していないもの」「原料が遺伝子組み換え食品でないもの」等を規格している。天然醸造の調味料や天然塩を規定することは現時点では考えていないが、今後の参考とする。
Q)東大和市としてどういった給食を目指しているのか。何かこだわっていることはあるか。またその評価をどのように行っているのか。
市)安心安全で栄養バランスのとれた、おいしい給食を目指している。手作りにこだわり、地場産の食材を使用したビーツコロッケや紅茶ケーキ、「だし」やシチュー類の「ルー」なども手作りである。評価については、日々の残菜量の確認と、毎日の学校の管理職の検食で分量、味付け、彩りなどについて評価をしている。
Q)使用している半調理品や調理品は。
市)半調理品は、シュウマイ、ハンバーグなどを、調理品はゼリーを提供している。
Q)魚や野菜は残食が多いと聞くが、理由についてなにか掴んでいることはあるか。
市)理由は特段把握していないが、一般的に食べにくいのではないか。
Q)サラダのドレッシングはクラスに1本配られ、使いきれない分は捨てている。配膳前にかけて混ぜるのだが、味加減がうまくいかないということも聞くが。
市)残ったドレッシングを廃棄していることについては課題意識をもっている。他市では調理の段階でドレッシングを和えているという例もあるが、野菜の食感を残すことも必要であり、調理の工夫で対応が可能なのか研究していく。
※ 「手作りにこだわっている」ということですが、半調理品や調理品も使われていることが分かりました。食育には「おいしい」が一番です。ぱっと見の豪さとか、子どもに人気のものということではなく、丁寧に作られた本当においしいものを子どもたちには味わってほしいと思います。
Q)栄養士はどのくらい給食の様子を見ているのか。
市)全体で月に2~3回程度の各学校で行う食育授業に併せて様子を把握している。今年度から1校に配置されている栄養教諭が可能な限り巡回し、給食センターの栄養士と共有している。
※ 給食内容の評価は管理職の検食で行っているということですが、子どもの食べている様子から、メニューごとの食べやすさや、量や形状など、チェックすべき点は大いにあります。「残さず食べましょう」と子どもに教えるだけではなく、残す要因について把握するなど現状の給食の評価をきちんと行うことが必要です。
Q)地場野菜はどのくらい使用しているのか。
市))地場野菜は2024年度は野菜の総使用量の約8.7%。2023年度の約9.8%とくらべ1.1%ほど減少している。夏の猛暑酷暑により野菜の収穫量が減少したためではないか。
Q)給食を作る側と農家さんとのコミュニケーションを深める取組みは。
市)「給食センターで使用する野菜の出荷調整会議」で地元生産者と意見交換を行ったり、給食センターの栄養士が地元生産者の畑に行き、給食で地場野菜を使うことについて話をしている。今後も対話を重ねていきたい。
Q)学校給食への保護者の意見としては、食べる時間が短いということがあるが。
市)小学校では25分程度、中学校では20分程度の喫食時間であると捉えているが、学校の状況によりスタートが遅れてしまうなど考えられる。確保できない場合は適宜学校で対応している。
※ 給食時間全体が小学校では40~45分、中学校では30分ですので、準備と片付けの時間を考えると「小学校では25分程度、中学校では20分程度」の食べる時間を取れるのか疑問です。
Q)東大和市の学校給食をみんなで考えていかれる場が必要では。
市)学校給食センター運営委員会には栄養士が事務局職員として参加をしている。今年の2月には給食の試食をし、意見交換をした。
※ 「学校給食センター運営委員会」は保護者や学校長や学校医、保健所職員などが委員ですが、栄養士や調理員、公募の市民が入って給食について話し合っている、という自治体もあります。東大和市でも「給食のあり方」まで話せるような会があるとよいと思います。
Q)学校給食への喜多方市産米の導入についての検討状況は。
市)2025年7月に喜多方市を訪問し、喜多方市の担当課や現地のJAと直接意見交換をした。導入できる時期などの詳細は決まっていないが、引き続き検討を続けていく。
※ 市としての食育への考えや描くビジョンについては、明確な答弁はありませんでした。食の大切さを教えながらも食事時間が短か過ぎたり、残さず食べようと言いながらもドレッシングの残りは捨てている、など矛盾も感じます。中には、給食で子どもたちに健康な食生活を伝えようと完全米飯給食としている自治体もあります。東大和市でも一貫した考えを持って取組むことが求められます。