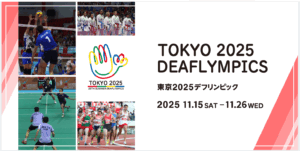【2025年 第3回定例議会報告】一般質問①「その人の望む暮らしを支えるものになっているのか ~ ひとり親家庭の支援について」
「ひとり親家庭の相対的貧困率は44.5%」といったことは広く認識されるようになりました。貧困対策や安定した職業に就けるための支援が必要、と言われます。しかし、ひとり親家庭の抱える困難は、仕事・家事・育児をひとりで担うことで疲弊していたり、時間的にも精神的にも余裕がなかったり、そのことから健康面の不安や問題があったり、孤立しやすいといったこともあります。経済的な安定はなくても、働き方を緩めたいというニーズもあります。そういったひとり親家庭の置かれた状況を的確に捉えた支援が行われているのか、質しました。

≪ 2.ひとり親家庭の支援について ≫
Q)東大和市のひとり親家庭の数は。
市)正確には把握できないが、「児童育成手当」の受給者数は2025年3月末現在733人であった。※「児童育成手当」は所得制限内(扶養1人であれば、2024年度は398万4千円)のひとり親が受給できるもの。
Q)ひとり親からの仕事に関する相談はどういったものがあるか。また支援の状況は。
市)増収のための転職、育児との両立のための資格取得などの相談がある。2024年度実績では、母子・父子自立支援プログラム策定事業が2件、母子家庭等自立支援給付金支給事業が5件の利用。
Q)利用が少ないが、ひとり親家庭の現状やニーズを把握するための調査を行ってはどうか。
市)国で行っている「全国ひとり親世帯等調査」の結果を参考にしいる。
Q)ひとり親家庭ホームヘルプサービスはどういったものか。
市)市内に居住し20歳未満の児童がいて、育児または日常生活に支障をきたしているひとり親家庭を対象とし、日常的な家事や子育てをサポートするもの。子ども家庭センターで相談・申請を行い、委託先の東大和市社会福祉協議会がホームヘルパーを派遣する。費用は所得額が基準以下であれば負担額はない。(参考)2人世帯=所得基準額3,604,000円(所得金額や人数により基準額は変わる)
Q)離婚前のひとり親家庭は利用できるのか。
市)現時点では利用できないが、2025年度に国・東京都の実施要綱に追加されたため、当市での運用を検討していきたい。
Q)2024年度の利用実績は。また利用実績に対する評価は。
市)1世帯に98回の派遣があった。適切に事業を実施しており、特段の課題はないと認識。
Q)対象となるひとり親家庭が、市内にはほかにいないという認識なのか。
市)ほかにいないとは考えていない。必要な家庭にサービスが届くような周知やお知らせが大事である。
※ 児童育成手当を受給しているひとり親は733人いて利用が1世帯というのは少なすぎます。「課題がない」との答弁ですが、対象となる人がほかにもいるとも認識。この支援は全国的に利用が少ないことが課題となっていますが、広く知られていない現状もあります。情報としてどこかに載せたり口頭で単に伝えるということではなく、その家庭の状況に応じて、「これを利用して生活を改善させていく」という支援のビジョンを持って利用を勧める、といったことが必要ではないでしょうか。
Q)離婚後に利用できる制度、離婚前の人が受けられる支援は。
市)離婚後は、児童扶養手当などの経済的支援、ひとり親家庭ホームヘルプサービスなどの子育て支援、母子家庭及び父子家庭自立支援給付金支給などの就労支援が利用できる。離婚に悩んでいたり別居中の人には、それぞれの状況に応じて生活の安定や自立のために利用できる支援制度を情報提供・相談支援を行っている。
Q)「児童扶養手当」を離婚前でも受けられる場合はあるのか。
市)「父又は母の生死が明らかでない」「父又は母が保護命令を受けた」「父又は母から引き続き1年以上遺棄されている」などの場合、父母が離婚前でも対象となるとされている。
Q)「父又は母から引き続き1年以上遺棄されている」という要件について、これまで居所が不明であったり、別居がアルコール依存や暴力行為といった問題行動からの避難である場合に遺棄と認められるものだった。しかし2022年に国から出された通知は、別居をしていてまだ離婚は成立していないが、子どもへの監護意思・監護事実が認められない場合を遺棄と認めると、認定基準を見直すものだが、この見直しについて当事者に届くように情報を発信する必要がある。市のホームページでも見直しについて広く周知できないか。
市)遺棄に該当するかは個別のさまざまな状況を確認したうえで適切に判断する必要があり、ホームページにへの掲載については十分な考慮が必要であると考えている。
Q)この手当の受給には自分から申請する必要があり、自分が対象となると知らなければ受けることができない。該当する人にこの情報を届けるためにどういったことを行うのか。
市)まずは窓口や電話などで相談してほしい。※ 認定基準の見直しを知らなければ、問い合わせもしません。
Q)当市でも認定基準の見直しがされたという認識でいいのか。
市)今まで国などでも担当者により対応が違うこともあったので、見直しをされたというよりは明確化されたという認識である。
※小平市など「「遺棄」の認定基準についての見直し」と市のホームページに明記、周知している自治体もあります。実質ひとりで育てているけど、離婚が成立していないことで対象とされていなかった人に、実態にあった手当の受給としていこうという「見直し」なのです。これは当事者にとってはとても大きなことです。せっかく開かれた支援を、市の対応ひとつで閉ざすことはあってはなりません。「どうしたら受給できるのか」という視点での相談者本位の判断、情報の周知を求めました。
Q)ひとり親家庭向けの情報を、例えば東大和市子育てアプリに「ひとり親支援」の項目をつくって掲載したり、プッシュ型で通知するなどできないか。
市)アプリでのひとり親家庭へのサービスなどの情報提供については、今後前向きに検討していきたい。
Q)ひとり親家庭の交流会を行えないか。
市)市において実施する予定はないが、立川にある「東京都ひとり親家庭支援センターはあと多摩」でイベントや交流会が行われており、必要に応じて市民に案内している。
※ 人とつながる余裕もない、情報を得る余裕もない、というひとり親家庭に対して、その人たちに届くよう情報を伝えることや、いかにつながりをつくれる地域としていくか、ということがまさに必要なことだと思います。。「自立して暮らす」というのは誰かに頼らず暮らしているということではなく、支え合える関係があって暮らしていることではないでしょうか。地域で安心して暮らしていくために、制度があるということだけでなく、つながりがつくれるか。そういった視点での支援の在り方を求めて行きます。