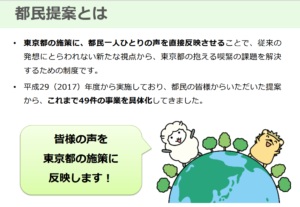【2024年 第3回定例会 一般質問②】「市立学童保育所第六クラブ」及び「きよはら児童館」の移転について
~ 移設される「きよはら児童館」の設計を子ども参加ですすめてほしい! ~
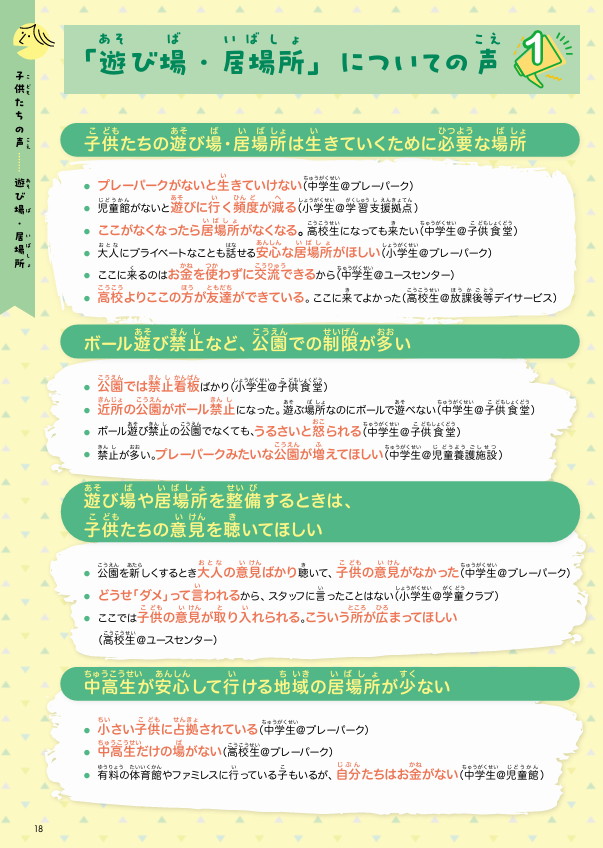
質問)どういう児童館となるのか。 ➡ 都営東京街道団地の建替計画において、同団地内に移設用地が提示されている。敷地面積は同程度で、建物や庭など基本的に同規模を想定している。
質問)中高生年齢の子が過ごせる施設としてどう考えるか。また夜間の開館については。 ➡ 中高生などの青少年の居場所が求められており、幅広い年齢層が共有できる施設となるよう必要な設備などを考えていく。夜間の開館については、職員体制や他の児童館のとの整合性もあり、現状は検討していない。
要望)子どもが集える場となるよう、学習できるスペースや、中高生年齢が集いやすいようにWi-fi環境を整備するなど、その年代の意見を反映してほしい。
質問)不登校の子が日中行ける場とすることについては。 ➡ 開館時間内で自由に過ごすことはできるが、自分の居場所と捉えられるパーソナルスペースの確保などの問題もある。不登校への対応は学校との連携を図ることが必要。
要望)通信制高校の子が日中過ごすとか、高校などを辞めてしまった子が集える場とすることなども含め、検討してほしい。
質問)設計策定のスケジュールについて。 ➡ 設計のスケジュールは定まっていない。国や東京都の補助金等について調整している状況である。
質問)どのように意見を聴取するのか。 ➡ 学童保育所や児童館の利用者や保護者、中高生など18歳までの青少年から意見を聴取したい。紙やWeb等でのアンケートのほか、インタビューにより、文字では上手く表現出来ない子どもの意見を聴取する、16~18歳の子に対してはSNSを活用するなど。
質問)聴取した意見の反映や検討の仕方については。 ➡ 集めた意見を整理・分類し、内容を的確に捉えて検討することが必要である。財政面や効果等を考慮し、各児童館の職員の意見なども広く集めて検討したい。
質問)検討委員会など、市民や子どもが議論をして決定に関われる検討の仕方についての考えは。 ➡ 同規模の施設・用途であることが基本。時間の制限もある。もらった意見からニーズを捉え、反映できる仕組みをつくっていく。
質問)例えば、図書室について検討するとか、遊具やおもちゃ類を検討するなど、部分的にでも子ども参加でできないか。 ➡ 児童館が出来上がってからのことになる。児童館の職員が子どもの意見を聞くなどして、どういった形で実現できるか工夫をしていきたい。
要望)裁量があるというのが大切で聴取した意見を反映するだけではなく、少しでも子ども参加が進むように求める。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回児童館をつくることは、子ども参加をすすめるチャンスではないかと考えています。市にはぜひ、検討や決定まで子どもが関われるようにすすめてもらいたいと思います。そして児童館が完成したあとも、子どもが主体的に活動できる場とすること。児童館の運営を子どもが実行委員会をつくって担っている、という例もあります。また18歳までの子どもが利用するようになれば異年齢の子どもの活動もできると思います。イベントを企画して実施したり、子どもが活き活き過ごせる場となるよう、今後も提案していきます。